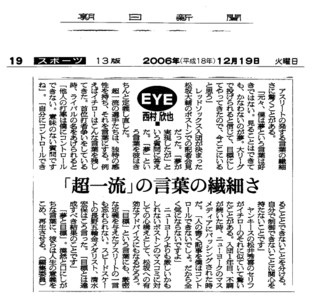リンクベイティングに触発されたエントリータイトル.
皆さんご存じであるように,私は保守派の人間であり,保守的な立場を取る.
私が保守派でなくてはならない唯一の理由を説明してみたい.
なお,このエントリーに触発されて保守派に転じることはお勧めできない.
「保守派かっこいい!」程度の考え方で保守派はやっていけない.
深層の深層から保守派が滲み出るような思想がないとダメ.
保守派の対極的存在といえば,革新派であろう.
私は革新派の考え方もスタンスも何もかもが嫌いでならない.
それこそが,私が保守派でなくてはならない唯一の理由である.
革新派は常に現状を何かに置き換えようとする.
表立っていうならば,現状をより良い状態に進めるために,新しく革めるのである.
聞こえはものすごく良い.
だが,少し慎重に考えていただきたい.
現状を示す状態Aがある.
革新派は状態Aをより良くするために,改革案を提出し,状態Bへと遷移させる.
よく考えよう.
新しく革めることを革新というのだ.
つまり,現状Aを状態Bで置き換えるのだ.
いうなれば,ほぼA∩B=φである.
さらに,状態Bから革新が起き,状態Cに移行したとしよう.
この状態では,ほぼB∩C=φであり,当然ながらA∩C=φである.
何故ならば,A∩C≠φだとするならば,それは革新ではなく,後戻りである.
革新派は絶対に自らの改革が失敗であることを認めはしない.
だからこそ,如何に状態Bよりも状態Aが優れていたとしても,
状態Aに後戻りすることはなく,新しい状態Cへと導くのだ.
もっと言おう.
革新派は常に革新を期待している.故に,革新派である.
革新し,革新し,革新して,革新し続ける.
つまり,いつまで経っても革新は終わらない.
要するに,不安定.
革新派は決して安定を求めない.
さて,保守派は一体どうであろうか.
保守派は現状を守り続けることを信条とする.
古き良き伝統を守り,今も守り続ける.
過去を,歴史を,伝統を守り続けることの難しさがわかるだろうか.
その苦労たるは,革新のそれとは比べものにならない.
現状を守り続けるということは,時代や世代などのあらゆる障壁と戦い続けることである.
私は言いたい.
革新とは,保守できない弱い人間が逃げるための手段であると.
革新の名の下に,低きに流れているだけではないのだろうか.
「○○な風習なんて時代遅れ」
「××の礼儀は必要ない」
「古くさい考え方なんてかっこ悪い」
「めんどくせぇから守らなくてよくね?」
保守はその流れに逆らい,より高きに留まり続ける.
水は低きに流れ,人の心もまた低きに流れる
攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG 第23話「橋が落ちる日 MARTIAL LAW」より.
よく保守派は勘違いをされる.
現状に満足している.新しいことを嫌う.何もしようとしない.
現状を守るということと,現状に満足し呆けることは,同義ではない.
保守は古き良き伝統を守り続けるのだ.
丁寧にいうならば,「良いものはできるだけ維持するべき」という考え方だ.
もうお分かりだろうが,良いものは守るが,良くないものは改善する.
当然,より良い状態へと改善を促していくのだ.
保守は良いものを守るために,改革することを常に忘れてはいけないのだ.
忠義も礼節も上下関係も伝統も重んじる.
それでありながら,常に現状に満足しない.
だからこそ,私は保守派でなくてはならない.